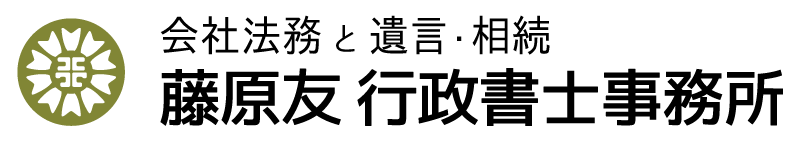遺言書の作成
遺言作成と終活サポート
大切な家族を守る遺言と,その周辺の制度利用をトータルでバックアップします。相続対策は,分割対策・納税対策・節税対策・手続対策の4本柱です。具体的に,「終活」のメインは遺言ですが,実は他にも便利な制度がいくつかあります。
成年後見についても広く知られてきているのではないでしょうか。他には,エンディングノートの利用,家族信託(民事信託),保険の活用,生前贈与などがあります。これらを組み立てて,将来の安心につながる方策を一緒に考えられればと思っております。
「遺言のすすめ」ページは→こちら←になります。また,ご質問やご相談は,お問い合わせページよりご連絡下さい。
遺言作成サポートは,通常,数日〜1ヶ月程度かかります。
自筆証書遺言作成時のフロー
自筆証書遺言作成の場合の流れは次のようになります。
-
-
- step 1 お問い合わせ・相談予約・無料相談
- まずはお問い合わせフォームやお電話等からご連絡いただき,無料相談をご利用下さい。
あらかじめ,必要となる書類や,事前準備について丁寧にご説明いたします。
ご依頼頂く場合の見積もりもこの時点で提示します。
-
- step 2 ご依頼
- ご確認いただいたのちに,正式にご依頼ください。
着手金のお振込があった時点で,正式なご依頼とさせて頂いております。
(相談のみをご利用の場合,2回目以降の相続相談料は7,000円/時間となります。)
-
- step 3 打ち合わせ・書類収集
- 打ち合わせと書類収集等を行います。①予定相続人を確認し②予定相続財産となるものの範囲を確定し③相続対策の方針を確認します。④遺言者ご本人の意思に反するところがないかどうか,再考すべき点がないかどうかの確認をします。
手続対策用「エンディングノート」もお渡ししております。
-
- step 4 自筆証書遺言の作成
- 原案の通りで問題が無いことをお確かめ頂き,全文を自筆にて清書をお願いします。
作成した遺言をその通りに実現するための,執行手続きについてもお任せいただけますので安心です。
-
- step 5 保管
- 自筆証書の場合,保管方法も重要なポイントになります。基本的には,封をして配偶者や信頼できる第三者に保管をお願いすることになります。銀行の貸し金庫を利用する場合は,注意が必要です。
-
書類取得費用等,全て込みの料金で見積もりを提示しております。見積もりに際してのご質問・ご相談は→こちら←をご利用下さい。
当事務所では,単に書類の作成方法を指南するのみではなく,先述の通り4つの相続対策の柱を持って,お客様(ご本人およびそのご家族様)にとって安全安心な終活のお手伝いをしたいと考えております。
とりあえず書き方だけを教えて欲しい,という場合はページ左のメニューより,テンプレート集をご覧になって下さい。
その他のご質問や無料相談の予約はお問い合わせページよりご連絡下さい。
公正証書遺言の場合
自筆証書公正証書のメリットは,大きく分けて以下の3つです。
- 公証人によって法的に確実性の高い(確定判決と同等の)書面を作ってもらえること
- 作成後は公証役場にて保管されるため,改ざんの恐れがないこと
- 遺言執行時に,裁判所による「検認」の手続きが不要になること
反対にデメリットは,次の2つになります。
- 自筆の場合に比べて作成に手間がかかること
- 数万円程度の追加費用(公証人手数料)が必要なこと

当事務所では,遺言作成後の安心を第一に考え,公正証書による遺言をして頂くことをお勧めしております。
そもそも,遺言の目的の一つは後の紛争予防ですから,裁判所と同等の公的機関である公証役場に介入してもらえる公正証書は,同目的を達するために大変有効であると言えます。
しかも,遺言公正証書の原案作成・公証役場提出書類の収集・遺言作成時の証人(2名)の手配も一括して承りますので,お客様にとっての手間は自筆証書遺言の場合とほとんど変わりません。安心してお任せ下さい。
公証人手数料
| 種類 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|
| 証書の作成手数料 | (財産の価格) 100万円以下 100万円超200万円以下 200万円超500万円以下 500万円超1,000万円以下 1,000万円超3,000万円以下 3,000万円超5,000万円以下 5,000万円超1億円以下 1億円超3億円以下の部分 3億円超10億円以下の部分 10億円超の部分 | 5,000円 7,000円 11,000円 17,000円 23,000円 29,000円 43,000円 5,000万円ごとに13,000円を加算 5,000万円ごとに11,000円を加算 5,000万円ごとに8,000円を加算 |
| 遺言手数料 | 全体の財産が1億円以下の場合 | 11,000円を加算 |
| 遺言の取消しの証書の作成手数料 | 11,000円(財産の価額に応じた手数料額の2分の1相当額が11,000円を下回るときはその額) | |
| 役場外執務 | 病床執務手数料 日当 旅費 | 通常の作成手数料の2分の1を加算 1日2万円(4時間以内1万円) 実費 |
| 正本・謄本の交付 | 1枚につき250円 |
秘密証書遺言の場合
秘密証書のメリットは,公証人や行政書士等の証人を含む,全ての人に遺言の内容を知られないという点です。
作成方法は,作成した遺言に署名押印し,封筒に入れて遺言書の印で封印し,公証役場へ証人2名と共に赴いて手続きをするという流れになります。
行政書士には法律上の守秘義務(行政書士法12条・22条)が課せられておりますので,特に秘密にしたい場合はもちろん,身内の方を含めた第三者に事実を知られる可能性は極めて低いです。また,専門家にも秘密にするということは,遺言の内容について相談できないということになりますので,先述のメリットはむしろデメリットにもなり得るかもしれません。
遺言の見直し,変更
「かつて書いた遺言の内容を変更したい」ですとか,「遺言を書いた当時と今とでは状況が変わったのだが,そのままでも良いのか」といったご相談も常時受け付けております。→こちら←からお問い合わせ下さい。
遺言について
遺言の目的
遺言には,次のような目的があります。
- 相続争いを防止する
- 財産の承継者を決める
- 自分の思いを死後に伝える
遺言が無いと困る7事例
遺言が無くてはならない,あるいは特にあったほうが良いという事例が,次の7つの場合です。
- 法定相続分とは異なる分け方をしたいとき
- 子供がいないとき
- 内縁の妻がいるとき
- 前妻との子がいるとき
- 相続人以外の人に財産をあげたい(寄付をしたい)とき
- 事業を行っているとき
- 財産について、不動産の割合が高いとき
→こちら←のお役立ち記事でも説明していますので、ご興味のある方はご覧になってください。
遺言の方式(種類)
遺言の種類は全部で6つあります。普通方式が3種類,特別方式が3種類です。このうち,特別方式は緊急時のものですので,ここでは割愛します。特に,普通方式のうちの自筆証書と公正証書が主な遺言になります。
1.普通方式

1)自筆証書遺言
「自筆」証書の名の通り,全文を自筆します。パソコンで作成して印刷する・誰かに書いてもらうということができません。
作成した日付の記載・署名・押印がない場合も,要件を満たさずに無効となってしまうので,必ず書くようにしましょう。
また,筆記具は万年筆やボールペンなどを使用し,鉛筆等消えてしまうおそれのある筆記具は使用しないようにしましょう。
他には,内容について解釈上誤解を招くおそれがない記述となっている必要があります。
幾通りかに読めるあるいは曖昧であるという場合,遺言のせいでかえって混乱を招いたり,争いの種になってしまったりということがございますので,繰り返し読み返して,必要があれば専門家にチェックを依頼しましょう。
比較的簡単に作成できる自筆証書遺言ですが,公正証書と比べたときの大きなデメリットは,遺言者の死後,家庭裁判所にて検認の手続が必要になるという点です。
当事務所では検認の必要がない,公正証書遺言の作成をおすすめしております。
なお,民法改正等により,自筆証書遺言の形式についての緩和と,自筆証書遺言でも検認の必要がない遺言の保管制度が始まりました。これらについてお役立ちページでご説明していますので、ご興味がおありの方は→こちら←もご覧ください。
| 項目 | 正しい | 誤り |
|---|---|---|
| 方式 | ○自ら全文を書いて記名・押印する ○日付の記載がある | ×人に頼んで書いてもらう ×ワープロやパソコンで作成して印刷する ×音声や映像で伝える |
| 筆記具・用紙 | ○ボールペン ○万年筆 ○筆ペン | ×鉛筆 ×熱を加えると文字が消えるペン |
| 表現方法 | ○人違いが生じない工夫 ○財産の特定 ○期日等を指定する場合はその指定 ○その他誤解を生じ得ない表現 | ×幾通りかに読める表現 ×その他曖昧な表現 |
2)公正証書遺言
遺言者と証人2名(計3名)が公証役場に赴き,公証人が作成します。
遺言者が公証人に口授してそれを公証人が証書にするという方式なのですが,前もって原案を作成しておき,当日は公証人がその原案を読んでくれ,遺言者が間違いのないことを確認するという流れになりますので,手続きはスムーズです(当日の所要時間は1時間程度)。
証人が2人必要になりますが,この証人に親族等の利害関係者はなることができません。
通常は,行政書士や弁護士など,公正証書原案の作成を依頼した専門職が証人に就任します。
また,健康上の問題で公証役場へ行けないなどの場合,公証人がご自宅や介護施設,病院等へ出張もしてくれます。
自筆証書との大きな違いは,数万円の公証人手数料がかかるというデメリットはあるものの,先述の通り検認の必要がないという点と,3通作成された公正証書のうち1通は公証役場に保管しておいてもらえるので,紛失のおそれが無いという点はメリットです。
また,形式上の不備が起こり得ず,作成時の本人の意思に関して、後々争いになりづらいという点でも安心です。
3)秘密証書遺言
遺言の内容について,完全に秘密にすることができます。公証人や専門職にも秘密にできます。
公証役場へ出向いて証人2名と手続きをする点は公正証書遺言と変わりませんが,予め作成した遺言(自署でなくても構いません)に署名押印して封筒に入れ,遺言に押した印で封印をしたものを持参します。
遺言が作成された事実については証明してもらえますが,内容について秘密にしてもらえることになります。
自筆証書同様に,遺言者の死後家庭裁判所にて検認の手続が必要になります。
2.特別方式
隔絶地にいる場合や危急時など,緊急のときに作成する方法です。前もって準備する方には特に必要ないですので,今回は割愛します。
「遺言の書き方で不明な点がある」「遺言の内容はこれで大丈夫なのか」「遺言が見つかったけれど,その後の手続きをどうして良いか分からない」など,お困りの際はお問い合わせページよりご連絡下さい。
初回の相談・出張相談は無料です。
行政書士には法律上の守秘義務がございますので,安心してご相談頂けます。